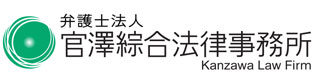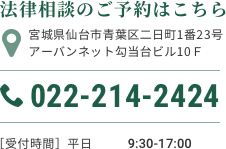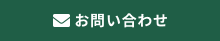メールマガジン2025年2月号
2025年09月01日
こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
寒い日が続きましたが、春の陽気も感じられるようになってきました。
今年は花粉が多く飛ぶそうです。
花粉症の皆様、当事務所相談室にはティッシュボックスを備え付けてありますのでどうぞご利用ください。
さて、メールマガジン2025年2月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆—————————————-
1、法務コラム
「道路の穴に落ちた…誰かに損害賠償請求できる?」 弁護士 渡邊弘毅
2、「生成AIは世界を変えるのか」 弁護士 長尾浩行
3、3月12日法務セミナー開催のご案内
———————————————-
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 【法務コラム】
「道路の穴に落ちた…誰かに損害賠償請求できる?」
弁護士 渡邊弘毅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●はじめに
埼玉県で道路が突然陥没し、トラックが転落した事故が話題になっています。
私も転落時の映像を見ましたが、通過のまさに直前に穴がボコッと空いており、正直言って避けようがない印象を受けました。
このような事故に遭った場合、誰かに損害賠償を請求できるのでしょうか。
●国や地方公共団体が管理する道路の場合
国や地方公共団体が管理する道路で事故が発生した場合、国家賠償法が適用されます。
国家賠償法2条1項には、「道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に欠陥があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体は、これを賠償する責任を負う」と規定されています。
ここでいう「欠陥」とは、「道路が通常有すべき安全性を欠いている状態」を指します。
例えば、今回のように道路に穴が空いていたり、舗装が壊れていたり、橋の手すりが壊れていたりする場合や、工事中に適切な標識や防護柵が設置されていない場合などが該当します。
ただし、道路の管理者が予見できない事故や、欠陥の発生が避けられない状況であった場合には、損害賠償請求が認められないこともあります。
●私人が管理する道路の場合
私道で事故が発生した場合、その道路の所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。
民法717条1項には、「土地の工作物の設置または保存に欠陥があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と規定されていますので、これを根拠に私道の占有者に対して損害賠償を請求することになります。
●損害賠償請求のポイント
損害賠償請求を行う際には、まず事故の証拠をしっかりと保全することが重要となります。
特にドライブレコーダー映像があれば非常に有益です。
また、事故現場の写真や、目撃者の証言などが有力な証拠となりますが、これが集まるかどうかは不確定かと思います。
加えて、警察に事故の報告を行い、事故証明書を取得することも重要です。
●被害者の過失と過失相殺
損害賠償請求を行う際には、被害者自身の過失も考慮されることがあります。
例えば、速度超過や、前方不注意で避けることが容易にできた、と認められた場合には、過失相殺が適用され、賠償額が減額されることがあります。
そのため、まずは注意して事故に遭わないようにする、ということが第一であることは言うまでもありません。
皆様もご安全に!
以上
(弁護士 渡邊弘毅)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「生成AIは世界を変えるのか」
弁護士 長尾浩行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ChatGPTを嚆矢とする生成AIが日々進化発展し、生成AIに関するニュースを聞かない日はないといっていい状況になっています。
どうやら「すごいもの」らしい、ということは伝わってくるものの、何がどうすごいのか、果たして私たちの人生や生活の何をどう変えてくれるのか、(もし本当なら日々の業務をどれだけ楽にしてくれるのか)、は正直よくわかりません。
さらにはあまりに次々と新しい何かが生まれ、変化が速すぎてついていくこともなかなかしんどいなという感じがしています。
日々「新しい何か」が生まれていること自体が日常になり、感覚がまひしてしまって、個々の「すごいもの」にいちいち反応していられないとも感じます。
とはいえ新しい何かについていくのはしんどい、フォローするのも面倒くさい、と言って放っておくのもまずいよなと思います。
技術や社会の進歩についていけなくて、取り残されるのも困りものです。
生成AIについては、インターネットが普及したときに匹敵すると言う人もいます。
インターネットが普及する前と普及した後とでは確かに私たちの生活は大きく変わっています。
インターネットのない生活はいまでは考えられず、もはや異なる世界線にいるようです。
はたして生成AIもそれくらいのインパクトがあるのか、実際のところは大したことないのかはしばらく様子を見るしかないのですが、90年代初頭のインターネットの黎明期を振り返ってみると、パソコンに14Kくらいのモデムをつないでインターネットに接続して、ヨーロッパのどこかの大学の研究室のコーヒーメーカーにどれくらいコーヒーが残っているかが日本にいながらにして確認できる、というのはどうでもいいことだったと思いますが、それでもこの技術は世界を変えるのかもしれないとぼんやり感じていた気がします。
実際にインターネットが世界を変えるにはさらに数年あるいは10年近くの時間と、スマートフォンの普及を待つ必要があったと私は考えていますが、生成AIも、これと付随する別のイノベーションが組み合わされば、本当に世界を変えるかも知れません。
若いころと違って新しいものについて行くのもなかなか大変なのですが、セミナーに行ってみれば「まずは使ってみることです」とアドバイスしてくれます。
習うより慣れろというのは先端のテクノロジーが相手でもあてはまるのでしょう。
法律分野で調査に使ってみると、理路整然と間違える感心するほどのハルシネーションをすることはままありますが、分析の対象を限定し、当事者双方の主張を対比させてみると思わぬ視点を提供してくれたりもします。
だからといってこのコラムを生成AIに書かせているわけではありません。
これは生身の人間である、私が書きました。
以上
(弁護士 長尾浩行)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3月12日法務セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※開催は終了しました。
【セミナー概要】
──────────────────────
テーマ: 訴訟リスクに対応する労務管理のポイント(有期雇用)
期間を定めた労働契約である有期雇用は、柔軟な人材管理を行なうことができるため、企業においてよく利用されています。
他方で、労働者の立場が不安定であること等から、同一労働同一賃金、無期転換ルール、雇止めに関する規制等、守らなければならないことが多数存在します。
今回は、有期雇用契約の基本的な知識や労働条件明示の昨年の改正点等と共に、それぞれのルールの主な注意点を、近時の裁判例等も適宜ご紹介しながらお伝えします。
ポイントを押さえ、今後の労務管理にぜひ役立てていただきたいと思います。
皆様のご参加をお待ちしております。
──────────────────────
講師: 浅倉 稔雅(弁護士)
──────────────────────
日時: 2025年3月12日(水) 15:00~16:00
──────────────────────
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あとがき
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
スマホにログインすればAIがサポートを始め、アプリを開くたびにAIのサポートが必要か確認されるようになりました。
もちろんとても便利で私も利用しますが、使う側のモラルも大切だなと感じます。
ときどき証拠として写真や動画を出すことがありますが、そのうち「この写真・動画はディープフェイクではない」ということも証明しないといけないのだろうかと頭をよぎるこの頃。
正しい情報と作られた情報を見分ける方法はあるのかAIに聞いてみたいと思います。
今月のメルマガは以上です。
次回は3月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。
以上