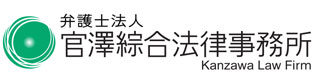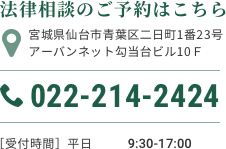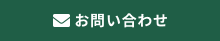メールマガジン2025年1月号
2025年08月27日
こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
1月1日より法人として執務を始めました。
メールマガジンは大きな変更なく、継続して発行いたしますので、引き続きご覧くださいますようお願いいたします。
さて、メールマガジン2025年1月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆—————————————-
1、法務コラム
「職種限定合意がある場合の配転について」 弁護士 浅倉稔雅
2、「法律業界におけるAI活用の取り組みについて」弁護士 渡邊弘毅
3、2月12日法務セミナー開催のご案内
———————————————-
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 【法務コラム】
「職種限定合意がある場合の配転について」弁護士 浅倉稔雅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、職種を技術職に限定する等の「職種限定合意」がある場合の配転について書きます。
配転(配置転換)は、労働者の配置の変更であり、職務内容又は勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものといわれています。
いわゆる転勤などもそうですね。
皆さんの会社の就業規則にも、「会社は、業務上の必要性がある場合には、配転を命じることができる。」等の規定が置かれており、そのような規定を根拠として、配転命令が出されていると思います。
令和6年4月26日の最高裁判決は、職種限定合意(職種や業務内容を限定する合意)がある労働契約についてのものでした。
同判決は、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該同意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」と述べました。
同判決は、従前の見解からしても当然のことを述べているように見えます。
しかし、実は、職種限定合意がある場合でも、経営状況の変動等によって当該職種を廃止せざるを得ない場合等は、正当な理由があれば、労働者の同意を得なくても別職種への配転命令が出せるという見解や裁判例も存在していました(実際、本件の原審でも解雇を回避するためであること等を理由として配転命令は適法であるとの判断でした。)。
今回の判決は、会社側の配転の必要性等よりも、労働者の意思に基づく職種限定合意を尊重した判断とみることができます。
では、会社としては、特定の職種や部門を廃止せざるを得ない場合、職種限定合意がある労働者に対してどのように対応すれば良いのでしょうか。
判決からすると、一方的な配転命令は許されません。
しかし、会社としては、労働者に対し、現実的に可能な他の職種への変更について同意してもらえないかどうか、打診した方が、トラブル予防になることは明らかです。
職種限定合意があったとしても、会社を変えず他の職種で仕事を続けたい場合もあるでしょう。
昨年4月から、労働条件明示の対象に、「就業場所・業務の変更の範囲」も加わっています。
職種限定合意をする場合には、当該職種が将来廃止された場合の対応についても考慮に入れておく必要があると思います。
以上
(弁護士 浅倉稔雅)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「法律業界におけるAI活用の取り組みについて」 弁護士 渡邊弘毅
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最近、あらゆる業界でAIの活用が模索されています。
我々の活動している法律業界でも例外ではありません。
ここで、当事務所での導入事例を含め、法律業界におけるAI活用事例についてご紹介したいと思います。
1、AIによる契約書チェック
当事務所では、LegalForceというAIによる契約書チェックサービスを導入しています。
これは、お預かりした契約書を所定のサーバにアップロードすると、AIがその契約の類型(例えば売買契約・請負契約等)を自動的に判断し、当事者の立場(売主or買主、発注者or受注者等が選べます)によって、契約書上に存在する問題点や、加筆・修正したほうが良い点を重要度のランクを付けて示してくれるものです(当然、アップロードした契約書の中身等は厳重に秘密保持されますのでご安心ください)。
我々人間の特性として「あるべきでない条項があるとき、あるいは内容が変なときには気づきやすいが、あるべき条項が抜けている場合には気づきにくい」という傾向があります。
AIはそこのところをうまくカバーしてくれて「この条項抜けてるよ!」「こういう条項を入れたらいいよ!」というアドバイスをしてくれるので、なかなか有益です。
2、AIによる文献調査
もうひとつ、当事務所で導入しているAIサービスは弁護士ドットコムライブラリーです。
こちらは、サービス本体としてはいわゆる文献のサブスクリプションサービス(=定額で文献読み放題)なのですが、AIによる調査補助機能が付いています。
このサービスに対し例えば「占有移転禁止の仮処分における当事者恒定効が及ぶ範囲について教えて」と文章で質問すると、「あーそれな。この本のここに載ってるで」と文献の該当箇所を教えてくれます(実際は関西弁ではありません)。
ChatGPT等のAIサービスでは、ハルシネーションと呼ばれる「AIが嘘をつく」現象が起こることが知られていますが、ドットコムライブラリーのAIはあくまでも書籍の内容をベースに回答するもので、かつ、利用者自身でその原典を調べることができるので、最終的な情報の信頼度は高くなります。
3、その他のサービス
その他、当事務所ではまだ導入していませんが、国内では「法分野に特化したAIによる翻訳サービス」「AIによる損害賠償金額の算出」、海外では「AI弁護士によるリーガルリサーチ」なども実用化されているという話です。
時代の波に乗り遅れず、よりよいリーガルサービスを提供するために、これからもAIの活用を検討していきたいと思います!
以上
(弁護士 渡邊弘毅)
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2月12日法務セミナー開催のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※開催は終了しました。
【セミナー概要】
──────────────────────
テーマ: ゼロから始めるコンプライアンス:
チェックシートで会社のコンプライアンスを自己採点しよう!
御社では、コンプライアンス対策、どのくらいやっていますか?
「そもそもコンプライアンス対策と呼べるものは何もしてない」という会社や「やろうとは思ってるんだけど、どこから手を付けたらいいか分からない…」という会社、多いのではないでしょうか。
今回のセミナーでは、日本弁護士連合会が作成したチェックシートを基に、御社のコンプライアンス度をセルフチェックすることができます!
例えば「会社法上のルール」「労働問題・セクハラ・パワハラ」「取引先との契約」「IT」といった分野ごとに御社のコンプライアンス到達度が分かり、またその改善策もご提案できますので、ぜひご参加いただければと思います。
──────────────────────
講師: 渡邊 弘毅(弁護士)
──────────────────────
日時: 2025年2月12日(水) 15:00~16:00
──────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あとがき
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
日本でコンプライアンスという言葉が知られるようになったのは2000年前後からのようです。
元々合致する日本語がないので、私などは今でもピンとこない言葉だなと感じてしまいますが、少なくとも日本でも25年程度は歴史があることになります。
私が社会人になった頃には新人教育の一環に含まれていました。
最近の某テレビ局の問題などを見るとコンプライアンスやガバナンスを企業や働く人の意識に浸透させ、体現するのは難しいのだなと思います。
今回のセミナーのような機会に正しい知識を得て、自分の現状に落とし込んでいく努力は続けたいですね。
今月のメルマガは以上です。
次回は2月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。
以上